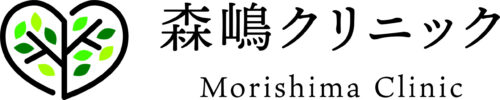はじめに
夏休みシーズンになると、国内外へ飛行機でお出かけする方も多いかと思います。
楽しい旅を万全の体調で楽しむために、機内環境の特徴とそこで起こりやすい健康トラブルを知り、 “備える・防ぐ・対応する” ポイントを押さえておきましょう。
目次
- 飛行機内は地上とどう違う?
- 飛行機で起こりやすい健康トラブル
- 時差ぼけ(Jet‑lag)対策
- 搭乗を控えた方がよいケース
- 旅行前の準備チェックリスト
- 機内での具体的な注意点
- 宇宙放射線と妊娠中の被曝量
- 旅行者血栓症(エコノミークラス症候群)のリスク別予防策
1. 飛行機内は地上とどう違う?
| 環境要因 | 機内の特徴 | 健康への影響 |
|---|---|---|
| 気圧・酸素 | おおむね標高 2,000 m 相当 (約0.8気圧) | 酸素飽和度が平均 3–4 %低下 |
| 湿度 | 10–20 %と砂漠並み | 粘膜乾燥・脱水 |
| 温度・気流 | 空調でやや低温、足元に冷気 | 体温調節ストレス、下肢の冷え |
| 宇宙放射線 | 高度・緯度・飛行時間で増加 | 妊婦・乳幼児は線量管理が必要(詳細は後述) |
2. 飛行機で起こりやすい健康トラブル
- 深部静脈血栓症 (エコノミークラス症候群)/肺塞栓症 (PE)
- 低酸素症による息切れ・頭痛
- 耳・副鼻腔の気圧障害
- 脱水・便秘・皮膚乾燥
- 胃腸不調・嘔気
- 時差ぼけによる眠気・集中力低下
3. 時差ぼけ対策
- 出発 2–3 日前から就寝・起床時間を目的地に 1 時間ずつ近づける
- 機内では目的地時間で行動(食事・睡眠)
- 到着翌朝の太陽光で体内時計をリセット
- カフェインとアルコールは控えめに
4. 搭乗を控えた方がよい主なケース
| 状態 | 推奨 |
|---|---|
| 最近発症した心筋梗塞・脳卒中 | 原則搭乗不可(主治医に相談を) |
| 治療中の 深部静脈血栓症・肺血栓塞栓症 | 完全治癒か治療安定まで延期 |
| 重症心不全・重度不整脈 | 医師同伴または酸素手配 |
| 妊娠 36 週以降(多胎は 32 週以降) | 航空会社の制限あり |
| 急性感染症(インフル・COVID‑19 等) | 搭乗延期 |
| 耳・副鼻腔の急性炎症 | 痛み軽快後に搭乗 |
5. 旅行前の準備チェックリスト
- 主治医へ相談
- 常備薬は機内持込み+予備 2–3 日分
- 弾性ストッキング を採寸、試着
- 旅行保険・緊急連絡先を確認
- 十分な睡眠と水分補給で出発当日の体調を整える
6. 機内での具体的な注意点
- 1 時間ごとに立ち上がってストレッチ
- 水分補給:1 時間あたり 200 mL を目安(心不全患者さんは主治医に相談してください)
- アルコール・カフェイン・高塩分食を控える
- 乾燥対策:保湿クリーム・点眼液・コンタクトは外す
- シートベルトは腰骨の上で常時着用
- CPAP・携帯酸素は事前に航空会社へ届け出
7. 宇宙放射線と妊娠中の被曝量
| 路線例 | 所要時間 | 線量の目安* |
|---|---|---|
| 羽田→福岡 | 2 時間 | 5–8 µSv |
| 成田→ホノルル | 7 時間 | 20–30 µSv |
| 成田→ニューヨーク | 13 時間 | 約 0.1 mSv |
* 太陽活動・航路で変動
- 胎児線量限度:妊娠判明後は 1 mSv/全妊娠期間、月 0.5 mSv が国際基準
- 一般旅行者が年に 1–2 回長距離便を利用しても 0.2 mSv 前後で安全域内
妊婦さんへのアドバイス
- 搭乗回数と飛行時間を最小限に
- 産婦人科の主治医と相談し、不安があれば日程変更を検討
8. 旅行者血栓症(エコノミークラス症候群)のリスク別予防策
| リスク層 | リスク因子 | 推奨予防策 |
|---|---|---|
| 低リスク | 40歳以上、肥満、糖尿病、脂質異常症など | こまめな歩行・足首運動・水分補給 |
| 中リスク | 下肢静脈瘤、心不全、経口避妊薬を含むホルモン療法、妊娠、出産直後、下肢の麻痺など | 弾性ストッキング +上記の一般予防策 |
| 高リスク | 深部静脈血栓症や肺血栓塞栓症の既往歴、6週間以内に受けた大手術、新血管系疾患の既往歴、悪性腫瘍など | 弾性ストッキング+医師の判断で抗凝固療法+一般予防策(主治医に相談を) |
一般予防策(全リスク共通)
- 1 時間に 1 回の歩行・屈伸運動
- アルコール・カフェイン制限+水分補給
- 到着後 4 週間 は下肢腫脹・息切れに注意し、異変があれば早めに医療機関へ
まとめ
飛行機内は「低気圧・低酸素・低湿度」という特殊環境です。
- 持病とリスクを把握し、出発前に必要な準備と主治医に相談をしましょう
- 機内では水分補給とストレッチを習慣化しましょう
※本記事は一般的な医療情報の提供を目的としており、個別の診断・治療を代替するものではありません。